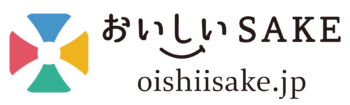“おいしい”が深くなる お酒と肴の相性診断 その鍵は「酸」?!

「肉には赤ワイン、魚には白ワイン」という誰でも簡単に覚えられるペアリングの大基本が日本におけるワインの需要を押し上げたというのは、昭和生まれの方ならもちろん、多くの方々がご存じの定説かと思います。もちろん、細かく言えばそう単純なものではないのですが、この大原則を目安にペアリングをしている方は今でも案外多いのではないでしょうか。
実際、この大原則、なかなか的を射ておりまして、肉、特に牛肉はデミグラスソースやグレイビーソースなどで食することが多いのですが、これらのソースには赤ワインがそもそも原材料として使われていますので、合わないわけがないわけです。一方、魚介にはブールブランソースやクリームソースなど白ワインが材料として使われているソースが多く用いられますので、やはり必然的に相性は抜群です。あとは濃淡の問題で、肉にしても魚にしても濃いソースを用いる場合はボディのあるワインが選ばれるというわけです。
こういうカラクリがあるので、「肉には赤ワイン、魚介には白ワイン」の黄金則は、長年にわたって多くの日本人を案外納得させてきましたし、現在も十分に通用すると考えても良いのではないでしょうか。ところが、日本酒にはこの種のペアリングの大原則がありませんでした。ワインの国内需要が伸びている最中に、日本酒はというと淡麗辛口ブーム「料理の邪魔をしない酒」が主流をなしていました。そして、ワインの需要はあれよという間に日本酒をはるかに超えるものになっていきました。戦後いつしか日本は経済大国と言われるようになり、暮らしもそれなりに豊かになっていき、家庭でも食事の時にお酒を楽しむようになりました。その時に、「今日は肉だから赤ワインにしよう!」という一歩進んだお酒と料理のペアリングの世界はとても新鮮で、おいしく魅力的な体験だったと思います。もし、日本酒も「料理を邪魔しない」ではなくて「料理を引き立てて、酒も旨くなる」を目指していたら、ちょっと景色は違っていたかもしれません。

そして、昨今ようやく「食中酒」としての日本酒が注目されるようになってきました。ところが日本酒はワインのように、赤や白がありません。じゃあ、どんな日本酒にどんな肴が合うのか、どうやって見分ければよいのでしょうか?
その鍵は「酸」です。実は、赤ワインと白ワインの場合も、それぞれに含まれる成分の中で重要な役割を果たしているのは醸造過程で生成される「酸」です。もちろん、果皮に含まれる渋味成分であるタンニンや色素であるポリフェノールも大きな違いの要素ではありますが、味わいやペアリングの内容を左右しているのはやはり「酸」です。
では、日本酒にはどのような酸が含まれていて、どんな酸とどんな肴が相性のよいペアリングとなるのでしょうか?
というわけで、おいしい日本酒ライターの蔵癖1号です。
今回は、日本酒と肴のペアリングを、日本酒に含まれる「酸」にスポットを当て、見ていきたいと思います。
ちょっと聞き慣れない単語とかがでてきて、ひっかかりもあるかもしれませんが、実際に試してみられたら、案外目からウロコものの発見があると思います。せっかく日本酒も楽しんでいただくのでしたら、肴とのペアリングを知って実践されることで、あなたの“おいしい”のレベルはグッと深まると思います。ぜひ、体験してみてください。
すぐに日本酒をチェックしたい方はこちら!
この記事の目次
日本酒に含まれる主な酸
日本酒にはお水とアルコールと糖分のほかにさまざま有機酸が含まれています。その代表的なものに「リンゴ酸」、「クエン酸」、「コハク酸」、「乳酸」があります。実は、この4つの酸が、酒肴がもつ酸と相性を織りなしてペアリングが成立していくことになります。
冷やしておいしい有機酸(冷旨酸)
クエン酸:爽快な酸味(吟醸系)
リンゴ酸:爽快で微かに苦味がある酸味(りんご)…冷やすと美味しい酸(吟醸系)
※吟醸酒、大吟醸酒の醸造過程で多く生成される酸で、冷やして美味しく感じます。
温めておいしい有機酸(温旨酸)
コハク酸:コクのある酸味(貝類)…温めると美味しい酸(純米系)
乳酸:渋味のある酸味(乳製品)…温めると美味しい酸(生酛系)
※生酛・山廃系・純米酒系の醸造過程で多く生成される酸で、常温から燗にすると美味しさが増します。
日本酒に含まれる主なアミノ酸
グリシン:甘味
アルギン:苦味(海藻類)
グルタミン:旨味(昆布)
アスパラギン:旨味(アスパラガス)
醸造中に分解されてしまう主なアミノ酸(酵母や麹菌の重要な成分)
イノシン酸:旨味(鰹節)
グアニル酸:旨味
代表的な酒肴に含まれる酸と日本酒の相性
日本酒に含まれる酸の内容と、どのような日本酒にどんな酸が多く含まれるのかを見てきました。しかし、酒肴・料理にも酸が含まれています。日本酒に含まれている酸と酒肴の酸をどのようにペアリングすると実際に“おいしい”が深まるのか。それではいよいよ、そのメカニズムを検証していきましょう。
どんな系統の日本酒にはどんな酸が多く含まれていたのか、振り返りながら検証をすすめていくと、合点がいくと思います。
魚料理
魚臭さの主な成分はトリチルアミンと言うアルカリ成分だと言われています。従って酸性調味料である味噌や醤油あるいは柑橘系を振りかけることにより中和され魚臭さが緩和されます。
同じ事は日本酒にも言えます。日本酒には多くの有機酸が含まれています。この有機酸がアルカリ成分を中和して魚臭さを消してくれます。それどころか日本酒のアミノ酸は魚特有の旨味を引き出す役割もしてくれます。
そこでその性質を利用すると魚も日本酒もさらに相乗効果があります。例えばさっぱりとしたイカの刺身や白身の刺身を醤油にレモンをたっぷり絞ったレモン醤油で食べるとクエン酸効果で魚の嫌味な臭さが消えると同時に更に濃厚な味わいとなります。このような食べ方には、少し冷えた吟醸系の日本酒が良く合います。
一方こってり系の鮪のトロや鯖の塩焼きなどには醤油そのものが持っている乳酸、アミノ酸がこってりした魚の成分と同じなので、醤油だけで充分な相乗効果があります。日本酒もアミノ酸が多い純米酒や乳酸が豊富な生酛系のぬる燗が相性抜群です。
貝料理
貝類にはコハク酸やアミノ酸成分が大量にあります。しかし同時に磯臭さのような独特の香りもあります。そこで、この臭さを消すにはクエン酸の力が役に立ちます。柑橘類やポン酢を使うとさっぱり系の本醸造酒や吟醸系はおすすめですが、例えば、浅利の酒蒸しや焼き貝、煮貝など、料理の仕方によってはアミノ酸の多い純米酒や、乳酸系の山廃・生酛の燗が非常に良く合います。
野菜料理
日本で食べられている野菜の多くは、際立った個性的な味が少ないので、日本酒には理想的な肴となります。特にナス料理は食べた後に、また日本酒が飲みたくなる効果もあります。そのような中でオクラとシシトウには特有な癖があります。しかしその癖の成分は日本酒の持つ酸類との適合性が素晴らしく良く、日本酒の味を引き出す役割さえもしてくれます。
また特筆すべきは大根です。生の大根を味噌、塩、マヨネーズなどを組み合わせた調味料で食べると、日本酒の旨味成分を引っ張り出す役割をします。マグネットでアミノ酸を引っ張り出す感じです。
豆腐などの大豆製品
大豆製品は成分上は最高に日本酒と合うはずです。その証拠に江戸時代には「豆腐百珍」「続豆腐百珍」と言う豆類を使った料理本が多く出版され、酒の肴として提案されてきました。
また利き酒をする際には豆腐が重要な役割をしています。次の酒に移る時に豆腐を口に含むと前の酒の存在を消してしまいます。これを応用すると日本酒がいくらでも飲めることになってしまうかもしれませんね。
塩辛
特に鰹の内臓の塩辛「酒盗」。思わず酒を盗んで飲みたくなるからこのような名前が付いています。発酵・熟成中に出てくるアミノ酸や有機酸が日本酒の各種酸類と見事に一致します。さらにチーズやヨーグルトと和えるとそれらの持つ乳酸が調和をはかり、さらに日本酒、特にぬる燗にした純米酒の味を引き立てます。またクエン酸を含むレモンをかける事によりさっぱり食べる事が出来ます。そうなると冷やした吟醸酒がぴったりです。
魚卵
魚卵の旨さはアミノ酸によるものです。しかし生臭さもあります。日本酒の持つアミノ酸がこの匂いを包んでくれるので、従ってワインより日本酒の相性が良いと言えます。同じ成分を含んだ純米酒が良いですね。
日本酒のタイプと相性の良い料理(一般論)
吟醸系
魚介の酢の物、イカの刺身・生うに(柑橘系を入れた醤油で)、大根のおでん、海老・イカ(塩とレモンで)、砂肝の焼鳥(塩とレモンで)

本醸造系
貝類(柑橘系を入れた醤油で)、海老・蟹(三杯酢で)、穴子の天ぷら(塩とレモンで)
純米系
鯖の塩焼き(醤油で)、ちくわ・がんもどきのおでん、穴子の天ぷら(天つゆで)、タレの焼鳥、焼売、青椒肉絲

本醸造系
ビーフシチュー、ローストした肉、パスタ類、鰻蒲焼、豚角煮、鯉甘露煮、蟹の唐揚、北京ダック、鶏鍬焼
おすすめの日本酒5選
それでは、いよいよオススメの日本酒です。
1.吉田酒造(福井県) 「純米吟醸 DRAGON WATER SILKY」
白麹のすっきりした爽やかな酸が特徴、純米規格の経済的なお酒
吉田酒造(福井県・永平寺町)は、近年、原材料の全てを自社圃場および蔵人の契約栽培田で収穫された酒米で賄うようになった。いわゆるドメーヌ酒蔵を目指す小さな酒蔵です。
「永平寺テロワール」を掲げ、「目が届く、手が届く、心が届く」を行動指標に、故6代目蔵元・吉田智彦氏が30数年前にはじめて永平寺の地で栽培をはじめた山田錦を、妻で7代目蔵元・吉田由香里さんと次女で杜氏の吉田真子さん、営業を担当する長女の吉田祥子さんが守り、少しずつ大きくしてきました。
ご紹介する「純米吟醸 DRAGON WATER SILKY」は、一般的には、日本酒の醸造には黄麹を使いますが、焼酎を造る時に使われる白麹を使ってを醸造しています。
近年、日本酒にも白麹を使ったお酒が少しずつ増えてきています。この白麹を使ったお酒の特徴として、クエン酸を多く生成します。クエン酸は、柑橘類や梅に多く含まれて、その特徴は、冷やしておいしい有機酸(冷旨酸)で、爽快ですっきりした酸味です。
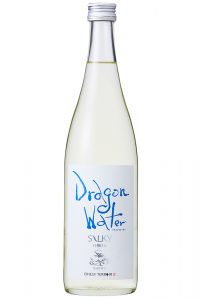
純米吟醸 DRAGON WATER SILKY
●価格 720ml:¥1,469(税込)
(2021年5月時点のサイト価格表示)
全量永平寺町産の五百万石のミネラル感とスッキリと爽やかな酸、マスカットの様なフルーティな香りです。ぜひ、冷やしてお楽しみください。
【おいしい飲み方】冷や◎ 常温〇 燗酒×
【合う料理】ミネラル感とスッキリと爽やかな酸が特徴です。冷やして美味しいクエン酸たっぷりなので、イカや鯛など白身魚の刺身に塩と酢橘やゆず、泉州ナスの糠漬け、あるいは、冷製トマトソースのイタリアン等と、とても良い相性です。
>>この日本酒をもっと詳しく知る
●原料米:五百万石100%(福井県永平寺町産)
●精米歩合:55%
●仕込み水:地下10mよりくみ上げた白山麓の雪解け伏流水(軟水)
●アルコール度:15.5度
●製造:吉田酒造有限会社(福井県吉田郡永平寺町北島7-22)
2. 高砂酒造(北海道)「純米酒 開拓魂」
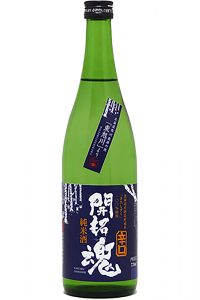
純米酒 開拓魂
●価格 720ml:¥1,414(税込)
(2021年5月時点のサイト価格表示)
3.大和川酒造店(福島県) 「伝家のカスモチ原酒」
5.栄光酒造(愛媛県) 「純米吟醸 松山三井【無濾過】」
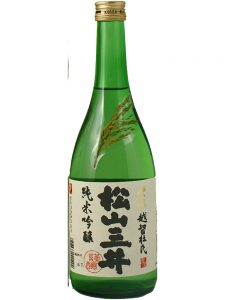
純米吟醸 松山三井【無濾過】
●価格 720ml:¥1,650(税込)
(2021年5月時点のサイト価格表示)
さて、いかがでしたでしょうか。
できる限り抽象的な相性論ではなく、実際の酒肴でイメージを膨らませていただけたらと思って展開してまいりました。どうぞ、みなさまもぜひお試しになってみてください。日本酒の“おいしい”の世界がグッと深まること間違いなしです!
これらの多くは、実際に試したことのあるペアリングです。
今回もありがとうございました。蔵癖1号でしたo(_ _o
*令和2年度補正 ものづくり補助金により作成
この記事は私が取材しました。
おいしい日本酒 編集部
デジタル・メディア『おいしい日本酒』は、唎酒師の資格を持つ編集長と、日本酒業界に精通するスーパーバイザーの監修のもと、日本酒に関わるコンテンツを、読者目線でわかりやすく、楽しくお届けします。